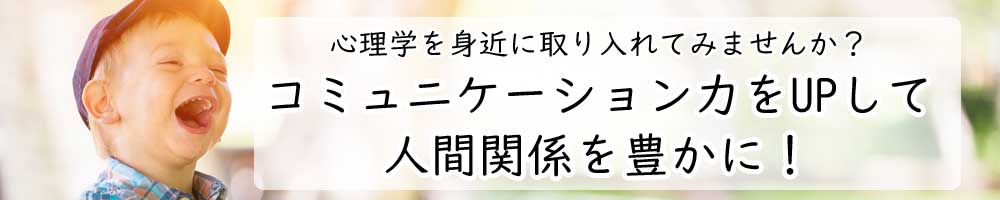今日は、認知的不協和と呼ばれる
心の中に生まれた矛盾を
解消させようとする心理
について説明します♪
目次
認知的不協和とは?
アメリカの心理学者
レオン・フェスティンガーが提唱したもので
人が自身の中で矛盾する認知を同時に抱えた状態や
それが引き起こす不快な感情にある状態
を、認知的不協和と言います。
「人が自身の中で矛盾する認知を同時に抱えた状態」とは、
どのような状態なのでしょうか?
それは自分の信念や、
それまでの行動内容とは矛盾する、
“新しい事実”を突きつけられた状態です。
その矛盾を、”自分の信念や行動”と、
“新しい事実”のどちらか一方を
否定することで解消しようすることを、
認知的不協和と呼びます。
不協和の解消方法は?
人は自分を正当化することで、不協和を解消する。
人は2つの矛盾を認知した時には
矛盾差のギャップを埋めるために
事実や行動が変えられない時には
自分の思考を変えて解消しようとします。
よく例題に使われるのが次の2つの思考法で
どちらも自分自身を守るために行います。
一つ目は「酸っぱい葡萄」の思考法で
このストーリーは聞いたことのある人も多いと思います。
酸っぱい葡萄と甘いレモン
酸っぱいブドウと甘いレモンの話を例に
不協和の解消について説明しますね!
酸っぱい葡萄
「手に入らないから価値が無い」
目標を達成できなかったことを
対象物を不当に低く評価して
現状を正当化する方向に解釈する心理
キツネが木の高い場所になっている
葡萄が欲しくて
飛び上がっても手が届かず
最後には
「どうせあのブドウは酸っぱくて、まずいんだ」
と言ってあきらめたお話です。
この話の中でキツネは、
「食べたい」と「手に入れられなかった」
という、
認知的不協和を「あの葡萄はまずい」
と思い込ませて解消しています。
このキツネのように
精神的な負担を軽くして
自分自身を守ろうとする心理です。
甘いレモン
「手に入らないから価値がある」
イマイチな結果でも、それが良かったのだと
正当化できる理由を探し出して
精神的な負担を軽くする心理
さっきの葡萄が取れなかったキツネが
帰り道に落ちていたレモンを拾って食べ
「このレモンは、さっきの葡萄よりも甘いに違いない」
と負け惜しみを言ったというお話。
認知的不協和の解消の具体例
では、認知的不協和の解消の
日常で見られる具体例を紹介しますね。
ダイエットの例が分かりやすいかと思います。
「ダイエットしよう!」
でも「冷蔵庫にはケーキが!」という状況の時、
食べたいと食べてはいけない
の2つの矛盾(認知的不協和)が発生しています。
この矛盾を解消するために
先ほどの酸っぱい葡萄と
甘いレモンの心理のどちらかを選びます。
A:ケーキをあきらめる
…ケーキを好きな自分(自分の信念や行動)を否定
B:ダイエットをあきらめる
… dietする(新しい事実)を否定
ということですね!
認知的不協和の実際の活用例
恋愛での活用例
好きな相手にお願い事をしてみることです。
普通、好きな相手に対して
自分が何かをしてあげたくなることが
多いと思いますが、
相手に何かをしてもらうのです。
嫌いな相手に何かをしてあげることはないので
自分がお願い事を聞いてあげているのにも関わらず、
「好きだからお願い事を聞いてあげている」
という風に、
自分の行動が納得いくように説明をつけてしまうのです♪
認知的不協和の理論や解消法についてのまとめ
まとめ:
1、認知的不協和とは、矛盾する認知を同時に抱えた状態や、それが引き起こす不快な感情にある状態
2、その状態を2つ理論のどちらかで、自分を正当化させることによって解消させようとする
認知的不協和を上手く応用してみてくださいね!